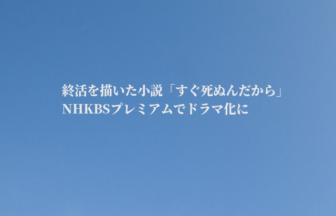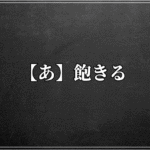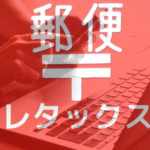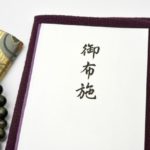本ページはプロモーションが含まれている場合があります。

約40年ぶりの相続法改正における「自筆証書遺言の保管制度」が令和2年7月10日からスタートします。
自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれるという制度になりますが、安全性としては向上することになります。
この記事では自筆証書遺言の保管制度をテーマに、要件や費用面・検認についてなど、わかりやすくまとめています。
あわせて公正証書遺言との比較についても触れていますので、是非最後までお読みいただき、終活する上で役立ててもらえたらと思います。
自筆証書遺言とは?
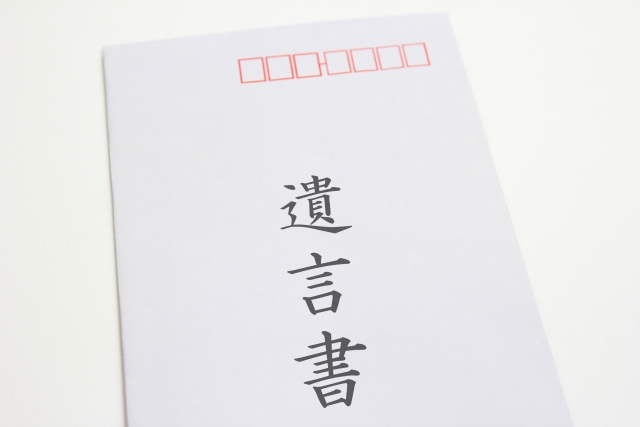
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、全て自分で作成する遺言書のことです。
ひと口に「遺言書」といっても、大枠的なところから以下のように分類されています。
| 普通方式 | ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 |
| 特別方式 | ・緊急時遺言 ・隔絶地遺言 |
自筆証書遺言での遺言書作成には、遺言の全文や氏名をすべて手書きで作成して、押印する必要があります。
そのため、パソコンなどで文字入力すると、遺言書としての効力を失ってしまいます。
しかし、2019年1月13日より財産目録だけはパソコン・ワープロで作成したものでも問題がないようになりました。
自筆証書遺言書の方式緩和
財産目録だけはパソコンやワープロで作ったものでも問題がない、これは法改正によるもので、「自筆証書遺言の方式緩和」といわれています。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されます。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意してください。
出典:法務省
2019年の1月13日以前・以後のことを簡潔に説明されているのがわかります。
法務省のホームページ内には、自筆証書遺言の方式(全文自書)、つまり全て自分で書く場合の緩和方策として考えられる例が参考資料として掲載されていますので、引用紹介させていただきます。
001279213
自筆証書遺言の書き方として参考になるかと思いますので、資料は目を通しておくとよいでしょう。
ちなみに財産目録とは、自身の財産を明確にするために、分かりやすく書き並べた文書のことを指します。
詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。
自筆証書遺言書の要件

自筆証書遺言書の要件とは、自分で書く・作成する遺言書に法的効果を生じさせるための条件です。
・遺言時(遺言書作成時)に意思能力があること
この2つが要件なので、例えば認知症などに見られる判断能力・意思能力が低下している状態で遺言書を書いても法的に認められなくなってしまいます。
※15歳未満は親権者等の同意の有無に関係なく遺言は無効
「改正で自筆証書遺言は何が変わったのか?」
というのをわかりやすくいうと
▼改正前
全文自筆(全て自筆)で遺言本文・日付・氏名を自筆しなければいけなかった
▼改正後
自筆で書く必要はあるが、財産目録はパソコンで作成・印刷したものでも可能になった
(不動産登記事項証明書や銀行口座の通帳コピーを目録として添付も可に)
ということになります。
自筆での遺言書作成において、改正以前は資産内容を全て手書きでというのは相当なボリュームとなりますし、労力もかかるものでした。
複数の不動産を所有している・財産の多い方ほど大変なことだったわけです。
財産目録を自筆しないでもよくなったことで、面倒な手間が省けることになったのです。
そのため、自筆証書遺言の方式緩和は「自筆証書遺言の要件緩和」ともいわれています。
改正後の気をつけるべき点としては、全てのページに遺言者の署名・捺印が必要だということです。
これは偽造防止のためであり、2019年1月13日より適用されています。
自筆証書遺言の保管制度とは?

「自筆証書遺言の保管制度」とは、令和2年7月10日から施行される制度のことです。
相続法改正に伴い、遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が成立したことにより、自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになりました。
以下、法務局のホームページより「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」の概要になります。
つまり概要の要点としては
・自筆証書遺言、つまり自分で書いた遺言書が法務局で保管してもらえる
・安全性が高くなる
・自宅等で保管の際、紛失などのおそれがある(遺言書の有無で相続争いに繋がるおそれ)が、保管してもらうことで紛失および亡失の懸念が解消される
ということです。
もっとわかりやすくいうと、自筆証書遺言の保管制度とは
「相続をめぐる紛争を防止するという観点で、法務局が自筆証書遺言書を保管しますよ」
ということになります。
法務局のホームページには、保管制度の周知用チラシのリンクもあります。
以下、制度の周知用チラシになりますので、概要とあわせて目を通しておくとよいでしょう。
注目すべき点を簡潔にまとめると、チラシの裏面(PDF2ページ目)に記載されている
保管は遺言者本人が手続きする必要がある
遺言書保管所(法務局)において保管されている遺言書は家庭裁判所の「検認」が不要
大きくこの2点だと思われます。
検認とは、家庭裁判所に申立てをして、遺言の存在や内容を確認してもらい、正しく効力を発揮できる物なのか判断してもらうことをいいます。通常、遺言者が亡くなってから遺族が遺言書(自筆証書遺言)を発見した際、検認を受ける必要があります。
この検認作業が保管されている場合は不要になることは、遺族からすると手間が省け、リスク回避にもなります。
公正証書遺言との比較

自筆証書遺言に係る遺言書(自分で作成した遺言書)の保管申請や、閲覧請求、保管事項証明書の交付を請求するには手数料が必要となります。
自筆証書遺言の保管制度における手数料は、どれくらいの費用なのか明確なところは記事執筆時点では公表されていません。
保管制度が施行される令和2年7月10日までに明らかになると思われます。
ちなみに、公正証書遺言の場合の費用面・手数料は下記の通りです。
(公正証書遺言とは、遺言をする方が内容を話して、公証人が記入して作成する遺言書です)
| 相続する財産の価値・金額 | 手数料の金額 |
| ~100万円 | 5,000円 |
| 100万円~200万円 | 7,000円 |
| 200万円~500万円 | 11,000円 |
| 500万円~1000万円 | 17,000円 |
| 1000万円~3000万円 | 23,000円 |
| 3000万円~5000万円 | 29,000円 |
| 5000万円~1億円 | 43,000円 |
| 1億円~3億円 | 43,000円 + 超過額5,000万円ごとに13,000円を加算 |
| 3億円~10億円 | 95,000円 + 超過額5,000万円ごとに11,000円を加算 |
| 10億円~ | 249,000円 + 超過額5,000万円ごとに8,000円を加算 |
※上記金額とは別途、相続財産が1億円以下の場合は11,000円が加算
その他、公証人への手数料以外に以下の費用がかかります。
| 公正証書遺言の謄本の発行手数料 | 250円(1枚) |
| 公証人による自宅や病院などへの出張 (自身が公証役場へ行けない場合に発生) | 10000円~20000円 |
| 病床執務手数料 (自身が寝たきりの状態で作成する時に発生) | 手数料に50%加算 |
| 証人を紹介してもらった場合の日当 (自身の友人等に証人を頼めない場合) | 5000円~15000円 (一人につき) |
自筆証書遺言の保管に関する手数料について、「高くても数千円ほどでは?」ともいわれているそうです。
そのため公正証書遺言作成にかかる費用よりは安く済むと考えられますが、自筆証書遺言の保管に関する手数料正式に定められるまでは正直わからないといった現状ではないでしょうか。
自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらが良いの?
一概にどちらとは言いきれないものですが、自筆証書遺言の保管制度が”相続紛争防止の観点”ということを考えると、今後はより注目されることになるのではないかと思われます。
自筆証書遺言の保管制度の費用的なところに関しては、法務省のホームページなどチェックするようにしておくようにしましょう。
まとめ

終活の観点から見ても、遺言書の存在は相続に絡む重要なものです。
今回は、終活する上で知っておきたい自筆証書遺言の保管制度について、わかりやすく解説させていただきました。
・自筆証書遺言とは、全て自分で作成する遺言書のこと
・2019年1月13日より自筆証書遺言における財産目録はパソコンやワープロで作成OKとなった(自筆証書遺言の方式緩和)
⇒財産目録を自筆しないでもよくなったことで、面倒な手間が省けることになった
・「自筆証書遺言の保管制度」とは、令和2年7月10日から施行される制度
⇒相続をめぐる紛争等防止の観点で施行される新制度
⇒保管は遺言者本人が手続きする必要がある
⇒遺言書保管所(法務局)において保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要
・自筆証書遺言に係る遺言書(自分で作成した遺言書)の保管申請や、閲覧請求、保管事項証明書の交付を請求するには手数料が必要
⇒公正証書遺言にかかる費用より安いと予想されている
引き続き自筆証書遺言の保管制度における手数料について、正式な額面がわかれば便宜追記したいと思います。
遺言書は相続問題に直結するアイテムであり、残された遺族が相続で揉めないようにという終活の本質的な意味でもある気遣いから作られるものです。
また、遺言書は相続人がいない場合でも頼りになるといえます。
以下の記事で相続人がいない場合の相続について解説していますので、是非このあとお読みください。